Real Face

カラオケに行った。
2020年6月の末のことである。
コロナが流行りだしてからカラオケ店は休業していたが、6月中旬に再開したので近所のジョイサウンドに行ってきた。
久々のカラオケである。一人カラオケである。
受付に行くと、僕の前の女性も一人カラオケに来ていた。
一人でどこかに行くとき、自分の他にも一人の人がいると安心する。
人は孤独だが、孤独である人同士がお互いの孤独を認め合うと、なんだかあたたかい気持ちになる。的なことを思う。
何を歌おうかとタブレットで探す。
「あの頃」検索。
僕の世代を検索すると、「Real Face」を見つけた。
あの、「Real Face」である。
KAT-TUNのデビュー曲であり、僕のデビュー曲でもある。
どういうことであろうか。
僕は中学時代、人生で唯一、ステージ上で観客を目の前にして歌ったことがある。
今でも当時のことを思い出すと恥ずかしくてお尻がかゆくなる。
僕には中学時代素晴らしきシンガー仲間がいた。
「G」である。
Gとは、部活も、クラスも2年から一緒で、休み時間や部活の合間にしょっちゅう二人でコソコソ歌を歌っていた。
だいたい、給食室の外の駐車場付近か、用務員のおっちゃんがいる技術室の外、それか校庭の向こう側のフェンスで隠れて歌った。
GLAYのHOWEVERや、ジャンヌダルクの振り向けば…、RIP SLYMEのブロウを歌っていた。
Gは最高のパートナーだった。
僕が普通に歌っていると、どんな曲でも独自のアレンジのハモリを挟んでくる。
ラップをしている途中で視線を合わせると、絶妙なタイミングで交代して入ってくる。
まさに阿吽の呼吸だった。
こんなにも歌が好きな僕らだが、音楽の通知表の「音楽への関心・意欲・態度」は最低評価のCだった。

3年生になり、Gと僕は、こんなに歌うのが好きなんだからなんかやろうということで、文化祭に向けてバンドを結成した。
これは相当勇気がいる決断だった。
文化祭の有志バンドなんて、学年一の美男美女かクソヤンキーしかやってはいけないものだと思っていた。
先輩たちを見ていてもそうだった。
僕たちはそのどちらでもない。
でも、僕たちは、どうしても自分たちの歌で学校を盛り上げてみたかったのだ。
ボーカルは言うまでもなくGと僕。
他のメンバーはオーディションを開いて選考することにした。
といってもほぼGと僕によるスカウトで決まった。
ドラムには他クラスのH、ギターにはNを迎えた。
二人とも音楽が好きだったのと、人間的な魅力があるのが決め手だった。
しばらくは4人で練習をしていたが、ある日他バンドを追い出されたというKが僕たちの仲間に加わりたいと土下座をしてきた。特に必要なパートがなかった為、彼をエアーギター&バク転担当とした。
伝説のバンドが結成された。
バンド名を決めようとしたが全然決まらなかったため、「決まらず」というバンド名に決めた。
決まらずは個性派揃いだった。
Hはドラムの練習をKの家の食器(皿と箸)を使って行っていた。テンションが上がりすぎて皿を何枚か割った。
Nは音楽室で借りたアコースティックギターで、当日はステージの端で理科室の椅子に座り、非常に丁寧に演奏していた。アンプを繋がない主義の為、彼が演奏している音は全く聞こえなかった。
Kはひたすらエアギターで暴れまくった後、間奏のところでバク転をしていた。演奏後、歌のアンコールではなく、バク転のアンコールが沸き起こった。
文化祭では僕らのような有志のバンドが他に2組ほどいた。
案の定、美男美女やヤンキーたちである。
しかし、僕らの発表はどのバンドよりも盛り上がっていた自信がある。
なぜなら僕ら自身がすごく楽しかったからだ。
僕は何百人もの生徒が見つめるなか歌った。
視力が悪くて初めてよかったと思った。
むかし、音楽会の練習で学年のマドンナ級女子に「こいつ全然声出してないじゅわーーん」と糾弾されたことがある。
そんな僕が、体育館のステージに立ち、大勢の前で、最高の仲間とともに「Real Face」を歌い上げていた。

終わった後、みんなの顔がピカピカ光っていた。
それぞれのテンションで、それぞれが自分の世界に入り、その世界観を共有していた。
メンバーとは、当日の演奏以降、この伝説のバンドについて口にし合うことがなかった。
強烈な羞恥があったのかもしれないが、振り返る理由がなかったからなのかもしれない。
反省も後悔も懐古もない。その日で全てが終わったのであった。
「Real Face」の歌詞に、「さぁ思いっきりブチ破ろう リアルを手に入れるんだ」とある。
僕の中学時代のこの経験は、それまで生きてきた中で一番自分を「ブチ破った」経験である。
そのおかげで、自分にはこういう一面もあるのだというリアルを知ることができた。
自分がなぜ自分をブチ破ることができたのか。
その一番の理由は、Gや、H、N、Kの存在があったからである。
彼らの存在そのものが、好奇心と恐怖のハザマでギリギリに揺れる僕の気持ちの中から、恐怖を取り払ってくれたのだ。
人は一人では生きられない。
誰かがいるから、自分のリアルを生きることができる。
不思議なものである。
誰かがいるせいで本当の自分を出すのが怖い。
それなのに、誰かがいるおかげでその恐怖が取り除かれるなんて。
人はそうやって、ギリギリで生きているんだ。



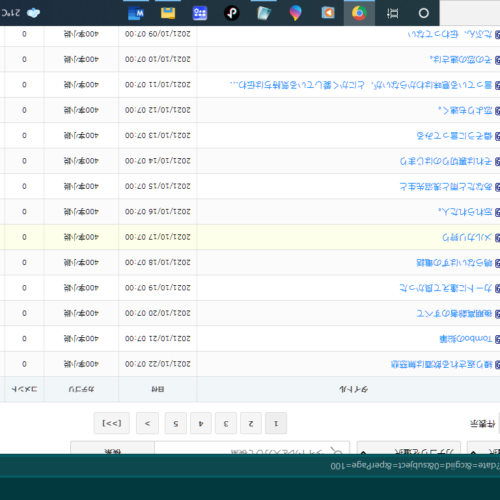


この記事へのコメントはありません。