生きづらい

息苦しくて目が覚めた。なにか悪い夢を見ていた気がする。原因はなんとなくわかる、
昨晩見ていたADHDについての動画だ。
ADHD(注意欠陥多動性障害)は、大人の発達障害なども認知されて最近どんどん有名になってきている気がする。おもな特性に多動・衝動性・不注意がある。
子どものうちには多動に目が向きがちだが、女性には不注意優勢型ADHDが多いらしい。目に見えてわかるものではないため、大人になってから困ることが多いそうだ。
ちなみに昨日見た動画で、不注意優勢型の女性があげていた特徴としては
・すぐぼーっとしてしまう
・興味が移りやすい
・ぶつける、こぼす、落とす が多い
・短期記憶が弱く、すぐに忘れてしまう
・時間やタスク管理が苦手
・集中が続かない
などが挙げられていた。
そして、そんな中でも適応しようと頑張りすぎてしまい、過適応という状態でい続けると、それが苦痛になってうつ病などになる人も多いそうだ。
そして、これらがまあなんとも私に当てはまってしまう。会議中に意識が飛んで話についていけない。すぐにスマホを落とす、そして壊す。無意識にぶつけていて足にはいつも青あざ。会話が飛躍する。できもしないのにすぐに仕事を引き受ける。1日に3回はスマホを探している。指輪やブレスレットなどのアクセサリーは落とす前提だからもはや消耗品。
苦しかったこと、辛かったことが全部ここらへんに詰まっていた気がしている。「過適応」という言葉があまりにもしっくりきてしまった。浪人時代、みんなできてることがなぜできないのだろうと本当に苦しかった。どんなに机周りに物を置かないようにしても、すぐに集中が散ってしまう自分がものすごく嫌だった。頭の中で喋っている誰かがずっとうるさかった。
こういった自分の嫌いなところが集約される場所があったことに驚いて、さらに、仕方のないことだと思えることに驚いて、でもきっと理解されない。だって私はそれなりに生きてこられた。
発達障害は当事者や周りの人が困っていて初めて「発達障害」になる。困っていなければただの個性で、性格である。
わたし自身、困ったことばかりではないのだ。発想力や想像力はわたしの飛躍しがちな思考から生まれるし、短歌が好きなのも飛躍した思考を収める箱になってくれているという理由に他ならない。じっとしていられないところも、わたしの好きな音楽になら生きてくる。自分の生きづらさと向き合いたかったから、たくさん本を読んで知識で乗り越える力は身につけた。そしてなにより、私は人に恵まれる才能がある。
それでも、だ。
それでも私は社会の中で上手に生きていける自信がない。甘えだろうか。甘えなんだろうな。でもどうやっても集中ができない。頑張り続けるのがうまくできない。締め切りはよっぽど好きか頑張らないと守れない。そんな人間がどうやって信頼されるというのだろう。信頼されようと思わなければいい。でも信頼されたい。この矛盾。
多様性が叫ばれる時代になった。それでも社会はすぐには変わらない。それどころか格差は広がる一方だ。新学習指導要領に則った教育が始まって、宿題がなくなったという声を聞いた。基礎学力は反復によってのみ身につくものもあろう。ますます家庭格差、学力格差は広がるだろう。そもそも、「主体的・対話的で深い学び」を「義務」教育で行うなんて本当にできるのか?と問いたい。それでも私は学校という場に魅力を感じてしまうのだけれど。
コロナの影響もあってか窮屈で仕方ない。息苦しくて生きづらい。どうやって生きたらいいのだろう。みんなどうやって生きているんだろう。
.
.
.
わるいこといやなことぜんぶ忘れちゃえ忘れちゃえって梅雨前線
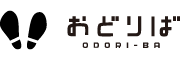





「生きづらさ」は、それぞれにあると思います。
耳が聞こえなかったり、上手く喋られなかったり。
それをどう感じるかも人それぞれなので、正解はありません。正解がないからこそ、もがくし、苦しい。
ただ、この記事が生まれる源には、そんな「もがき」や「苦しさ」を言語化できる力がある。
それはきっと、どこかで別の「生きづらさ」を抱える誰かの救いになると思います。そして、自分にとっても。
陰ながら、これからの表現活動も応援しています。